◆◆◆リレーエッセイ《夏》◆◆◆
夏のエッセイに、飯降かず「様変わりのお葬式」、本村映一“Every single day”、芝田敏之「映画『マルクス・エンゲルス』を観て」、石川 久「スマートフォン」を追加しました。
様変わりのお葬式 飯降かず
30年ほど前には葬式は町内・隣保班で執り行われた。「○○家のだれそれが亡くなったので、お手伝いに出てください」と知らせが回ると何を置いても一軒に一人とか二人とかが手伝いに行く。大抵このようなことに精通している長老が居て、役所への届けや祭壇作りお寺さんの手配、家族や親戚の精進料理つくり、受付、香典の受け取りなど全てを取り仕切る。
葬式のお手伝いに参加してこそ、その地域社会の一員と認められる。
だが、こうした葬式を執り行うのは、現代の生活ではだんだん無理が生じてきた。ほとんどの家が共働きで「お手伝いに出てください」と言われても仕事を休めない人も多く、参加できる人と出来ない人との間に気まずさが生じる。
そのころから、あちこちで葬儀会館が出来始めた。これは便利だ。町内のお手伝いも必要ないし、会場設営ほか全ては喪主がお金を払えば解決する。はじめのうちは親戚一同、職場の人、友人知人、近所の人など大勢参列した。
最近の傾向は、家族葬が多くなった。葬儀会館もこじんまりとしたものがよく利用されるようだ。親子兄弟だけで行い、したがって香典も「遠慮します」という事も稀ではない。
この30年ほどの変化は実に驚くばかりだ。時代の変化によって、合理性を追求する人が多くなり、それに合わせて雨後の竹の子のように次々と出来た葬儀会館、多くの人がこの流れに乗った。
近所の葬式のために会社を休む必要も無くなったし、あまり付き合いのなかった人の葬儀に形ばかりの香典を持って出かけなくてもあまり後ろめたくなくなってきた。同じ町内でもだれがいつ亡くなったのか知らないままに過ぎてしまう。この変化を合理性の上からだけ評価してよいものだろうか。失われたものはないのだろうか。
近所・隣保班で葬式を執り行うことによって培われてきた絆は大きく変化した。しかし絆のない社会がいいとは思わない。新しい絆を構築することが地域の課題だと思う。
"Every single day" 本村 映一
この言葉を某スポーツ新聞で見た。今年2月のプロ野球巨人軍キャンプの臨時コーチに就任した松井秀喜氏(巨人→米大リーグヤンキースなどで活躍)が、21歳で主力打者を期待されている岡本和真選手に贈った言葉らしい。ヤンキース時代の松井氏が当時のキャプテン・ジーター選手から教わった言葉だった。
その意味するところは、「日々の結果に一喜一憂することなく、結果を受け容れ、次に自分は何をなすべきかを考える」ことを繰り返す、とのこと。
何となく心に残る言葉だ。岡本選手は、6月から4番打者となり周囲の期待通りになってきているようだ。彼の成長には20歳で結婚した2歳年上妻の功績があるのかも。21歳にしては浮ついたところがない。
私は今、毎日結果を求められる立場にはないが、しかし自らが考え、鍛錬していくことを続けることは人生を豊かにしてくれるはずだ。Every single week,or month,or season,or year 、おっと、そこまでの余裕はない。
時には休養も必要だが、漫然と日を過ごしたくない。一喜一憂はしないつもりだが、今何をすべきかだけはしっかり見つめて生きたい。私が好きな歌手・大塚博堂(故人)に「小さな幸せでよければ」というシャンソン風の歌がある。
歌詞の中に「……何となく生きてゆくより ひたすら生きる方がいい……」に共感している。(2018.6 もとむら・えいいち)
映画「マルクス・エンゲルス」を観て 芝田敏之
2018年はマルクス生誕200周年にあたるという。この映画はマルクスの誕生日が5月5日であることから、4月28日のゴールデンウィークに封切りという念の入りようだ。
マルクスの伝記(たとえばフランツ・メーリング著「マルクス伝・1~3」〔国民文庫・大月書店〕)も大型本にして再刊したりして用意万端だ。要になるのは若い人にどれだけ関心を持っていただけるかだろう。
日頃は、自分が読者の場合、活字を読んで自分の脳裏に勝手なイメージを創りあげている。自分が作者なら、読者を飽きさせずにどれだけ豊かにイメージを想像していただけるかが勝負である。(少し大げさに書いたが文学の良し悪しはそれだけではないし、勝敗を決めるものでもない。
その点映画は、カメラに写る範囲だけでもイメージを創って観客に見せなければならない。)
この映画に期待したのは、200年近く前のヨーロッパの人々がどんなものを食べ、どんなものを着て生活していたのか。工場と町並みはどんな様子だったのか。これらの期待には、ひとつを除いて裏切られた。ひとつとは、イギリスのエンゲルス紡績工場の全景は見応えがあった。
これから観る人のために書くのをためらうが、妻イェニーが2人目の子を出産したときのこと。マルクスは「どっちだった」と尋ねる。イェニーは「女よ」と。それを聞いて思わず「またか」とつぶやく。すかさず「ほかに言うことはないの」ときついひと言。
労働現場や組合の中で、2人の主張が認められず「労働したこともない若造のクセに」と、殴られるエンゲルス。
電気もない時代、ローソクを2本立て、湧き上がってくるアイデアや構想を睡眠時間を削って書き取るマルクス。やがて身も心も疲れ果て突っ伏してうたた寝してしまうマルクス。明らかに映画から、人間マルクス、人間エンゲルスを描こうとする意図が伝わってきた。
ろうそくの明かりで朝まで執筆し、外が明るくなるころ、広げたノートに顔を付け、眠るマルクスの姿を見て、『資本論』を読まずして死ぬのは申し訳ない、もったいない」読みかけで放り出してある『資本論』を読み終わらないうちには死ねない、と強く思った。(2018.5 しばた・としゆき)
スマートフォン 石川 久
孫ができてから、小さい子に目がいくようになった。
先日のことである。地下鉄の車内で幼子を連れた女性にあった。朝の通勤時間だから栄駅での乗り降りは多く、席に座ることができない。名古屋駅で乗客がどっと降り、座席が空いた。女性は空いた席に座り、抱っこしていた男の子を膝の上にのせた。男の子は機嫌が悪いらしく、小さい声で泣きながら体をくねらせた。すると女性はカバンからスマートフォンを出して、男の子に見せ、あやしかけた。しかし、男の子の機嫌が直らず、手で払いのけようとした。
次の日も同じ親子づれにあった。名古屋駅で乗客が降りると、幼い子を連れた女性は席につき、男の子にスマートフォンを渡した。こんどは手に取り、画面をみている。ときどき指で画面を押さえている。動画はゲームのようだった。この光景を眺めながら私は複雑な気持ちになった。
軽い言葉 石原まこと
四年程前フェイスブック(FB)に夢中になっていた。最初は自己流で利用していたけれど、分からないことが多くネットで見つけた養成講座に申し込んでアカウント認証や画像の貼りつけ方等FBの基礎から応用までを勉強させてもらった。その講座の全国の受講生とお互い友達申請をし合い、講義の理解不足を補ってもらった。
旅行、ペット、日常生活などの報告を写真や短文にして発信し、「いいね!」やコメントで友達との交流を楽しんでいた。とくにシェアされると励みになりより良い文章をと心がけるようになっていった。
八十五歳の方(多分日本最高齢のFB愛用者?)からは返信でコメントが届いてそのままにしておいたらお叱りの言葉があり慌ててお返をしたり、同人誌に小説を投稿したと報告したら四人の方から読んでみたいと言われ贈呈して友好を深めていった。又誕生日が近づくと沢山のお祝いの写真入りメッセージが届き感激した。
ただ問題は毎日の生活で、朝、昼、夕とパソコンを開いてFBをチェックしなければ友達との交流が難しくなってきたことだった。リタイヤ―して十年、時間は有り余っているはずだが、町内のボランティアの活動もあり次第にFBで言葉を発信することを負担に感じるようになってきた。
FB 利用は知り合いとネットを介して友達になり写真や近況をやり取りし、そこから友達の輪を広げていくのが本来の在り方なのだろうが、俺の場合は同じ講習を受けているというだけで友達になった。友達の性格や癖など何も知らないまま言葉だけのやり取りをしていた。相手の歓心を買うコメントをしたり、当たり障りのない返信を返してみたり、綺麗ごとだけを言葉にしていた。真実の言葉が語られないことに次第に嫌気がさしてついにFBから遠ざかってしまった。
今になって思えば、このような言葉もそれなりに可愛げがあったのではと最近ようやく気が付いた。名護市辺野古の米軍新基地建設、「森友学園」への国有地の不当な払下げ、自衛隊の「日報」の隠蔽の問題等で数え上げればきりがないほど軽い言葉が飛び交い、嘘も真も言葉の使い方一つでどうにでもなると思われている節があるこの日本の政界。まだFBで発信してきた言葉の方が悪意のない分だけ貴重ではなかっただろうか。
最近は時々、FBを開き友達のニュースフィードへ飛んで近況を閲覧しているが、「いいね!」もコメントも何も返していない。
《執筆者紹介》
石原まこと 本名 石本達雄
一九四四年生まれ 新潟県出身 現在名古屋市北区
日本民主主義文学会 会員
同 名古屋支部支部員
ありがとう 石原まこと
「ガア、ガア、ガア」すごい咳だ。「クオ、クオ」今度は痰が喉に絡まってしまったようだ。四人病室のはすかいのベッドから聞こえてくるが、昼間、見かけた様子からすると八十をとうに超えたおじいさんだと思うが、大分苦しそうだ。気管支か肺が悪いのだろうか?
「ガーグー、ガーグー」カーテンで仕切られた隣のベッドからは往復のいびきが聞こえる。俺より少し若そうな人だったが、良く眠れるな、入院が長くてもう慣れたのかな。ほかの病室でナースコールが鳴っているが、看護師が廊下を小走りに走っていく音が聞こえる。
入院一日目の夜、これではとても眠れる状況ではない。家の近くの診療所で年一回の健康診断を受けたら、肺に影が認められた。このN医療センターを紹介され、検査の結果、肺がんの初期と診断され明日胸腔鏡手術でがん細胞を切除するという。この間一か月、検査、検査で慌ただしくてがん宣告を深刻に受け止める暇もないほどだったが、リタイヤして十年、身体にメスを入れるのは初めての経験で、いくらステージ1と言われても不安がないわけではない。
「グア、グア」まだおじいさんの咳が止まらない。ナースコールで教えてあげようか、あ、「ピンポーン」おじいさんが自分で押したようだ。
「どうされました?」
この病室の担当看護師なのだろうか、夜勤に入る前に挨拶があった若い娘の声だ。
「咳が止まらない、苦しくて」
「咳止めを飲みましょうか? 痰は飲んだら駄目ですよ、一回吸引しましょうね」
薬が効いたようで、漸く静かになった。往復のいびきは相変わらずだが、手術を前に体力を温存しとかなければ、少しでも眠りたいが。
「点滴を変えますね」
今度はおじいさんの隣のベッドから看護師の声が聞こえてきた。フウー、ついため息が出てしまう。
「ピンポーン」又おじいさんが看護師を呼んでいる。咳は止まっているが、何だろう。
「うんこ、漏れそう、トイレに連れてって」
「トイレに行くのは危険ですから、ここのおまるで用を足してね。はい身体を起こして移動しましょうね」
「出ました」
「こんなんじゃ出ないわ」
「ゆっくりやってください、終わったらお尻を拭きますからナースコールで呼んでね」
おならの音と共にかすかに臭いが漂ってきた。やれやれ、いびきをかいている人がうらやましい。
「ピンポーン」
「出ましたか?」
「少し出たけど、まだ出そう」
「それなら、おむつをしましょうかね。それなら安心でしょう」
紙の擦れる音が聞こえてくる。
「おむつ取ってくるから、少し待っていてね」
おむつか、俺もいつかは必要になる時が来るのだろうな。
まぶしい、懐中電灯の強い光が顔に当てられている。手で目を覆った。光は外れ、隣のベッドに移った。看護師が一人ひとり患者の状態を確認しているよう。
「検温をお願いします」
病室が明るくなり、看護師の声が枕元で聞こえる。朝方少しうとうとしていたようで、カーテンを開けベッドの傍に来たことも気が付かなかった。目の前の体温計を貰い脇の下に挟んだ。指をオキシメータに入れ、続いて血圧計が腕に巻かれた。採血が3本もある。
朝食が配られ始めた。
「朝食はないです」
カーテンの隙間から看護師の声が聞こえた。昨夜の夕食時は少量のおかゆを介護助師のおばちゃんが配膳してくれたが、朝は看護師が運んでいる。
「ありがとう」
イヤホンで朝ドラを見ていると、看護師がカーテンを開け挨拶した。
「手術頑張ってね」
「うん、今ありがとうって言った。俺に何で?」
看護師から感謝されるような覚えはないが?
「夜勤を無事勤めることが出来ましたというお礼の挨拶」
隣のベッドからも同じ言葉が聞こえてきた。さあ、手術まで一時間を切った。
《作者紹介》いしはら・まこと
名古屋民主文学会会員
日本民主主義文学会会員
中部ペンクラブ会員
私の文学修行 鬼頭洋一
今から30年ほど前のことである。
小説を書こうと何度も原稿用紙に向かったけれど、書いては破りの繰り返しで、なかなかものにできなかった。それが、当時はまだ稀だった妻の分娩に立ち会うことになり、その時の感動体験がすらすらと書けたのである。題名は「夫立ち会い」。私は33歳だった。小説を書いたら名古屋支部に入れてもらおう、とずっと思っていたので、当時の名古屋支部の支部長だったはらたはじむさん宛てに原稿を郵送した。
何日か経って、はらたさんから電話があり、地下鉄池下駅の近くにある喫茶店で会うことになった。よく晴れた土曜日か日曜日の午後だったけれど、季節は定かではない。たぶん秋だったと思う。はらたさんは、私が郵送した原稿を持参しており、テーブルの上に広げた。
何枚目、と言われてあわてて私はページをめくる。言われたことを書こうとボールペンを取り出そうとすると、それを遮るように、「あの、このメモはあとであなたにお渡ししますから」とはらたさんが生真面目に言った。はらたさんはメモ用紙を見ながら、誤字脱字から、言葉の選び方まで事細かく指摘して下さった。
家に帰り、私ははらたさんにいただいたメモを参照しながら大幅な修正をし、原稿を再び郵送した。それから何ヵ月かして、活字になったゲラが送られてきた。そこには当時の『名古屋民主文学』の編集長だった山本隆吉さんの手紙も同封されていて、最後のシーンはこんな風に書き直しては、と見本の文章が半ページ程書かれていた。私はそれを読んで、作品が甘くなってしまうと思った。せっかくの助言だったが元のままにした。
合評会は栄にあったマンション(山本事務所)で行われた。はらたさん以外は初対面の方々ばかりで、私はひどく緊張した。何を言われたかほとんど覚えていないけれど、松山薪子さんにオノマトペの使い方がダメだと指摘されて、成程と思ったことだけは強く印象に残っている。
あれから30年、名古屋支部の一員として小説やエッセイ等、短い作品を書き続けてきた。何度も褒められたりけなされたりした。批評してくれる仲間がいなければ、忙しい仕事をしながら作品を書き続けることはできなかっただろう。
定年退職して4年が経った。今、毎月の例会やその後の「飲酒文学」は、文学へ向かう私の原動力になっている。当り前のことだけれど、小説は一人でしか書けないし、一人では書けない。読みながら書く、書きながら読む。私は、名古屋支部のみなさんと、生涯現役で文学修業を続けていこうと思っている。
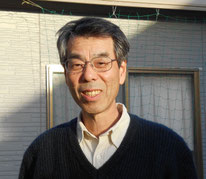
≪作者紹介≫ きとう・よういち
1952年1月生まれ。
日本民主主義文学会名古屋支部・運営委員
「わかちあい」にて第28回四日市文芸賞を受賞。
四日市市在住。
炊飯器を買いに 勝手三郎
10年間使っていた1升炊きの電機炊飯器が6月にこわれてしまった。この春に退職し、僅か2か月後の出来事である。働く妻に代わって家事を担うことになった私は、やはり相性が合わないのだろうかと消沈した。
この10年の間に父が亡くなり、3人の子どもは全て独立し、今は母と妻との3人暮らしだ。1升もいらないから、5合炊きの電気炊飯器でも買ってこようと思った。しかし数年前、ガスコンロを買った時に付いていた専用の3合炊き炊飯鍋があることを思い出し、使ってみた。すると驚いたことに、17分という短い時間で炊きあがる。コンロには3合炊き用のプログラムが組み込まれ、最初は頼りないほどの弱火だが、3分後にはゴーゴーと音を立て火力が強くなる。暫くすると重い蓋がボコボコと踊りだし、フツフツと熱湯をまき散らす。その様は凄まじく、世の中にこれほど熱情的なものがあるだろうかと感心した。
蓋を開けると米が立っており、食べてみるとそれは旨かった。冷めて電子レンジで温めても旨い。ジャーで保温しておくより余程旨い。妻も絶賛である。「よし次に買うのはガスだ」と決め、ガス器具店に行き、店員に聞くと、5合炊きは27分かかると言う。朝の27分は少々待てない。3合が5合になれば、6割増しで、熱量も比例し17分から27分になるのはもっともである。妻は飯が好きで、3合炊きでは1日持たない。やはり電気にしてタイマーをかけて使おうと思い直し、電気店に走った。店員からあれこれ説明を受け、値段を考え、これが一番という商品にやっと辿り着いた時、私は店員に、国家の機密を明かすかのごとく、ボソリと言った。
「ガスでやると重い蓋を持ち上げるようにボコボコと勢いよく炊き、それが旨い」
「そりゃ旦那さん、どんなにいい物でもガスにはかないませんよ」
店員は大きな声で、あっさりと言ってのけた。
私はどうしていいやらわからなくなり、3日間考えた。ガスにすべきか電気にすべきか。待っても旨い方がよいか、朝すぐ食べられる方がよいか。
人間は考えなければいけない。いい案が浮かんだ。圧力鍋だ。
普通ご飯を炊く水の量は、米の1.2倍としたものだが、圧力鍋は吹きこぼれないので、1.1倍にして、5合の米を最初から強火で炊いてみた。すると、圧力がかかるまで5分、3分間圧力をかけ火を止め、4分蒸らす。合計12分だ。これが旨い。今までの中で、つや、甘み、旨味、どれをとっても最高である。これなら、朝起きてすぐに火を付け、着替えや、おかずを調理している間に十分出来上がる。
飯が一人前炊けるようになって、私は主夫になった。
《作者紹介》かって・さぶろう
私の好きな歌『明日に架ける橋』 中江 明
人は誰でも自分の心の琴線に触れる歌と出会う事があるでしょう。私の場合それは、アメリカの「サイモンとガーファンクル」の『明日に架ける橋』でした。「君がへこたれて自分をちっぽけに感じる時、君の瞳に涙が満ちた時は、その涙をすべて乾かしてあげよう。僕は君の味方だもの。ああ、辛い時が来て、君に誰も友達がいない時は、明日に架ける橋のように、僕が身を投げかけてあげよう」(ポール・サイモン 一九六九 拙訳)という歌詞の内容には、一九六〇年代の公民権運動やヴェトナム反戦運動等で揺れるアメリカ社会を反映しながらも、それをヒューマンな自己犠牲の精神で包み込んだ、極めて高いフレンドリーな他者志向性が認められるでしょう。
私自身が実際にこの曲を知ったのは、このフォーク・デュオの実質上の解散後の一九七〇年代の半ばでしたが、高雅なピアノのイントロと、平易な言葉で紡ぎ出された美しくも気高い歌詞に一聴強く魅了された事を、今も鮮明に覚えています。私個人は大のクラシック音楽愛好者ですが、他面、一九六〇年代後半から一九七〇年代中葉にかけての欧米のロック・ミュージックやポップスをこよなく愛する者です。その中でも、今回ご紹介申し上げた、このサイモンとガーファンクルの文学的センスに富んだ楽曲世界は、一九六〇年代の、ビーチ・ボーイズらに代表される「能天気なアメリカ繁栄讃歌=平俗なラヴソング」の席捲下においては、ボブ・ディランらと共に異彩を放っており、今日、少なからぬ同時代のポップスが懐メロと化したのとは対照的に、時代を超えたリアルかつファンタスティックなメッセージ・ソングとして高く評価されて然るべきかと存じます。
それにしても、この『明日に架ける橋』のピアノ弾き語りは本当に難しい。私のピアノ=音楽的才能も、たかが知れているようです。
《作者紹介》 なかえ・あきら
『名古屋民主文学』編集委員
同誌に「反映論のさらなる深化のために~永井潔『芸術論ノート』および『反映と創造』を読む」を連載中。
 日本民主主義文学会 名古屋支部
支部誌 『名古屋民主文学』
日本民主主義文学会 名古屋支部
支部誌 『名古屋民主文学』